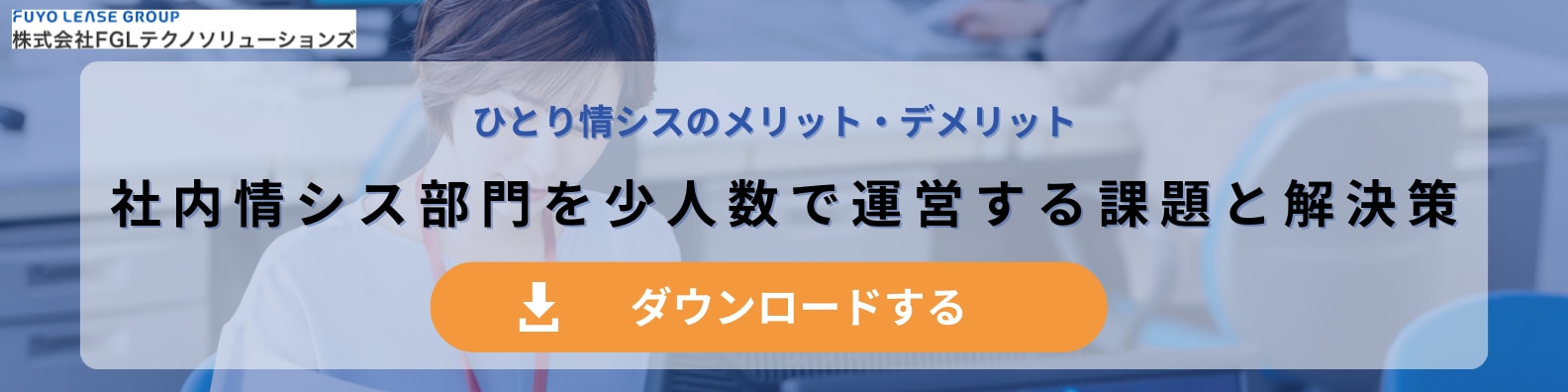社内システムの構築方法とは。開発ツールの選び方と内製のポイント
※2024年5月21日更新
IT技術の急速な進化や消費者ニーズの変化など、ビジネスを取り巻く環境がめまぐるしく変わる今、スピード感のある事業運営を行うために欠かせないのが“社内システム”です。
社内システムの構築方法には、自社での内製と外部への委託といった主に2つの方法が存在します。内製する際は、システムの運用方法に応じて開発ツールを選定する必要があります。
これから社内システムの構築を検討している企業においては、「内製にはどのような方法があるのか」「どのような開発ツールを選べばよいのか」など疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、情報システム(以下、情シス)部門や経営管理の担当者に向けて、社内システムを構築する方法、開発ツールの選び方、内製する際のポイントについて解説します。
なお、既存の社内システムを導入する手順やポイントについては、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
出典:総務省『令和3年版 情報通信白書』
目次[非表示]
社内システムを構築する方法
社内システムを構築する方法には、主にスクラッチ開発とパッケージ開発の2つがあります。
スクラッチ開発
スクラッチ開発とは、システムのすべてを一から制作・開発する方法です。要件定義から機能・デザインの設計、実装、テスト、運用に至るまでのすべてのプロセスを自社で対応します。
スクラッチ開発のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
▼メリット
- 自社の業務内容・フローに適した独自性の高いシステムをつくれる
- 要件に合わせて柔軟に機能追加ができる
- 長期間利用できる など
▼デメリット
- 初期コストが高額になりやすい
- パッケージ開発よりも開発期間が長くなりやすい
- 保守運用の負担が大きい など
パッケージ開発
パッケージ開発とは、既存のソフトウェアを購入・インストールして社内システムを開発する方法です。すべてを一からつくり上げるスクラッチ開発とは異なり、既製品を土台として必要な機能のみを追加・カスタマイズする点に違いがあります。
パッケージ開発のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
▼メリット
- フルスクラッチよりも初期コスト・開発期間を抑えられる
- 保守運用の負担が少ない
- トラブル対応が早く安定的に稼働する など
▼デメリット
- 多くの機能追加・カスタマイズを行う場合にコストが増加する可能性がある
- 業務フローの変更が必要になる可能性がある など
システム構築に用いる開発ツールの選び方
システムの構築に用いる開発ツールの選び方には、主に2つのパターンがあります。どのような方法でシステムを構築・運用するかによって、適した開発ツールが変わります。
自社の業務にシステムを合わせる場合
自社の業務に合わせてシステムを構築したい場合には、スクラッチ開発を行うことが一般的です。
ただし、スクラッチ開発には高度で幅広いプログラミングの知識・技術が必要です。自社で対応が難しい場合には、ノーコード・ローコードの開発ツールを活用してシステム開発を行う選択肢もあります。
▼ノーコード・ローコード開発ツールの特徴
- ソースコードの記述が不要、または最小限の記述のみで対応できる
- 直感的な操作で開発を行える
ノーコード・ローコード開発ツールを用いることで、プログラミングにかかる時間を短縮でき、システム開発のスピード向上につながります。
システムに自社の業務を合わせる場合
システムを基準として自社の業務を合わせるパターンでは、既存のソフトウェアを用いたパッケージ開発による対応が可能です。
現在の業務フローを調整しながら既存のソフトウェアに対するカスタマイズを行い、業務とシステムを擦り合わせる必要があります。
▼既存ソフトウェアの選び方
- 自社の業務に対して汎用性のある機能が備わっている
- 一つのパッケージで必要な機能を確保できる
- 予算の範囲内で必要なカスタマイズを行える
パッケージに含まれる機能やカスタマイズの範囲、拡張性などを確認して、自社の業務に対するフィット・ギャップ分析を行うことで、適したソフトウェアを選定できるようになります。
>>社内システム運用管理業務トータルサポートサービスに関する資料ダウンロードはこちら
社内システムを内製するときのポイント
社内システムを内製すると、自社の業務内容やフローに適した独自のシステムを構築できます。ただし、既存のシステムを導入する場合と比べて、人材やコストなどのリソースが必要になります。スムーズに作業を進めるためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
①現在の業務を棚卸しする
どのような社内システムを内製するのか、現状の業務を棚卸しして導入範囲と優先順位を定めます。
業務の棚卸しを行う際は、業務フローや作業内容、使用しているシステム・ツールなどを可視化できるフローチャートを作成することがポイントです。フローチャートによって棚卸しした内容を基に、システム導入の必要性が高い業務フローや改善が求められるシステムについて優先度を分けて洗い出します。
▼優先度の分け方
- フローが複雑で既存システムでの対応が難しい業務
- 現状維持したい業務
- 外部システムを活用する業務
独自性の高いシステム開発が求められたり、将来の拡張性が求められたりする業務については、システムの内製を検討する必要があります。
②システム構築の目的を明確にする
社内システムを構築する際は、目的を明確にしておくことがポイントです。
「どのような業務課題を解決したいのか」「何を実現したいのか」を明確にしておくことで、システム開発の手法や運用方法などを検討しやすくなります。
▼システム構築における目的の例
- 保守運用コストの削減
- 業務の効率化
- リモートワークの推進 など
目的に応じて内製化するシステムの範囲を決めることで、開発期間やコストを踏まえて計画的に作業を進められます。
③システムの要件を設定する
現在の業務課題とシステム開発の目的を明確にしたあとは、具体的にどのようなシステムを内製するのか要件を設定する必要があります。
▼システム要件に定める主な項目
- 機能
- 予算
- 可用性
- 信頼性
- 機密性(セキュリティ) など
システム自体の機能と予算だけでなく、継続して利用するための可用性や信頼性、セキュリティなどの非機能要件についても設定しておくことが重要です。
④リソースを確保する
社内システムの構築を計画に沿って進行するには、必要な人材や設備などのリソースを事前に確保することが欠かせません。リソースを社内で確保するのが難しい場合には、補うための施策を検討する必要があります。
▼社内リソースを補う施策の例
- 人材育成を同時進行で行う
- ノンコア業務を外部に委託する など
情シス部門や管理部門の業務負担が大きく、システム開発に充てる時間を確保できない場合には、ノンコア業務を外部に委託することも一つの方法です。
ITアウトソーシング(業務代行)でシステムの内製を効率化
社内システムの内製には、業務内容・フローに適したシステムを構築できるメリットがある一方で、システム開発のリソースを確保するのが難しいという課題があります。
ITアウトソーシング(業務代行)を活用すると、システム開発や環境構築を効率的に進めることが可能です。
▼ITアウトソーシングで補える業務例
- 社内サーバ・アプリケーションサーバの構築に必要な機器の選定や調達、セットアップ
- 拠点間接続や社内LAN工事などの回線手配からネットワーク装置のセットアップ、フロア内LAN工事
- 事務所立ち上げ・移転時に発生する外線・内線電話の工事 など
社内システムの構築や運用管理などを一貫して依頼できるITアウトソーシングサービスを利用することで、社内におけるリソース不足の課題を解決できます。
また、ITアウトソーシングでは、業務全体だけでなく部分的に委託することも可能です。社内システムを内製する際に発生する一部の業務を委託できれば、作業の効率化と開発スピードの短縮につながります。
ITアウトソーシングについて、詳しくはこちらの資料をご確認ください。
まとめ
この記事では、社内システムの構築方法について以下の内容を解説しました。
- 社内システムを構築する方法
- システム構築に用いる開発ツールの選び方
- 社内システムを内製するときのポイント
- ITアウトソーシング(業務代行)で委託できる業務
社内システムを内製で構築するには、スクラッチ開発とパッケージ開発の2つの方法があり、それぞれ使用する開発ツールが異なります。
スムーズに内製を進めるには、業務の棚卸しを行いシステム開発の優先順位と目的を明確にするとともに、自社に必要なシステムの要件を詳細に設定することがポイントです。
また、自社のリソースに課題があり、情シス部門や管理部門だけで対応が難しい場合には、ITアウトソーシングを活用する選択肢もあります。
『FGLテクノソリューションズ』の社内システム運用管理サービスでは、サーバの設置やネットワーク工事などのITアウトソーシングサービスを提供しており、社内システムの構築を支援いたします。専任のITコンシェルジュにより、貴社の業務内容や課題に応じたサービスをご提案いたします。
サービスの詳細については、こちらから資料をダウンロードしていただけます。