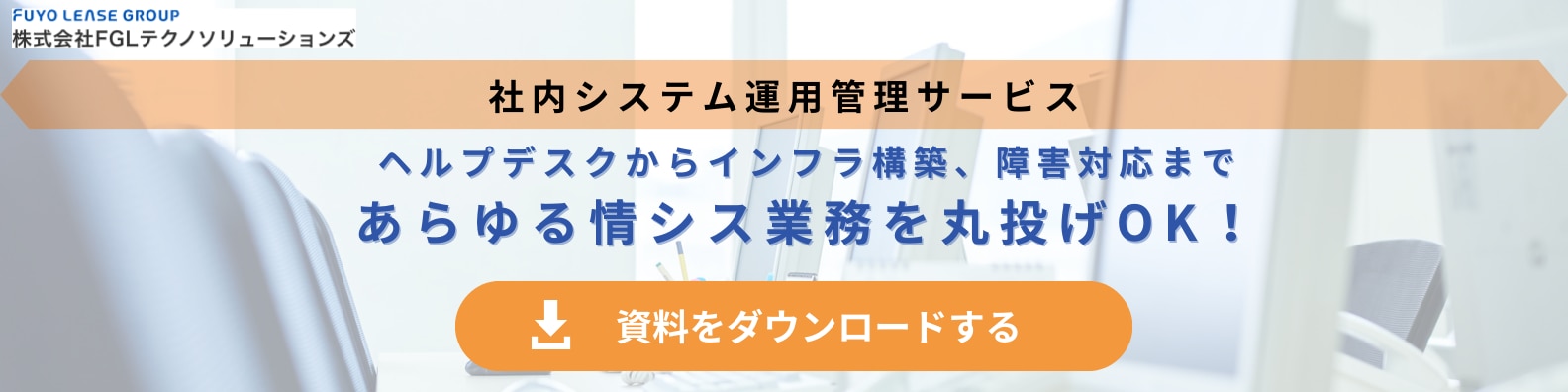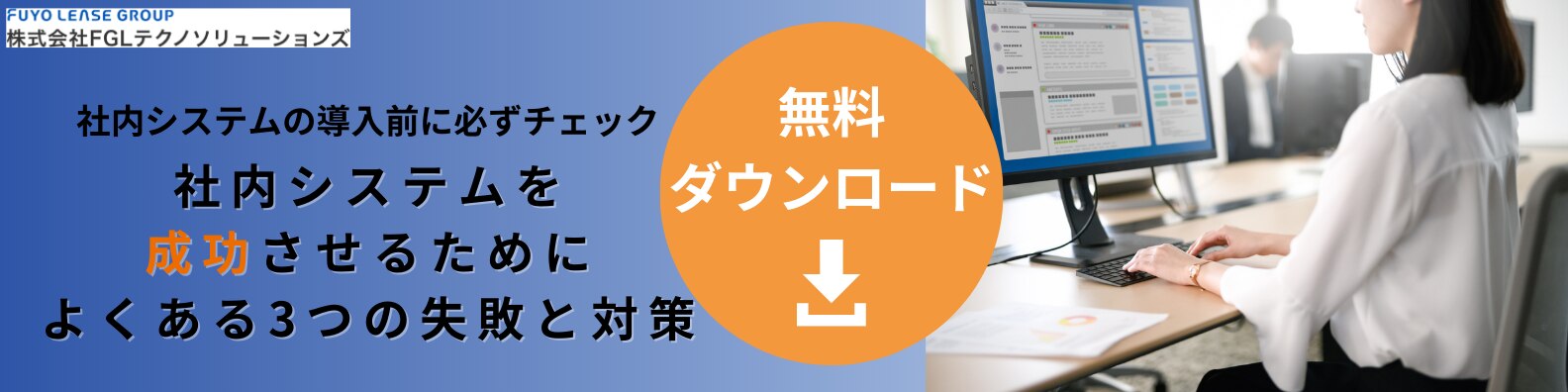社用携帯の監視方法とバックオフィスが押さえておきたい運用前の注意点
テレワークや外出先での業務が増えるなか、社用携帯は社員にとって重要な業務ツールとなっています。
しかし、業務利用と私的利用の境界が曖昧になることで「情報漏えい」「不正利用」「業務効率の低下」といったリスクが生じやすいのも事実です。バックオフィス部門や情報システム部門が適切に社用携帯を監視し、ルールに基づいて運用することは、企業のセキュリティと生産性を守るうえで欠かせません。
この記事では、社用携帯を監視する必要性や監視対象範囲、具体的な方法、そして運用時に注意するポイントを整理して解説します。
目次[非表示]
- 1.社用携帯の監視が必要な理由
- 2.社用携帯の監視対象
- 3.社用携帯の監視方法
- 3.1.①MDM(モバイルデバイス管理)
- 3.2.②位置情報の取得
- 3.3.③通話履歴や検索履歴の取得
- 4.社用携帯を監視する際の注意点
- 4.1.運用ルールの策定
- 4.2.従業員への事前説明
- 4.3.運用のしやすさの確保
- 4.4.社内教育の実施
- 4.5.セキュリティ対策
- 5.まとめ
社用携帯の監視が必要な理由
社用携帯の監視は、企業の情報資産を守り、業務効率を維持するために必要です。特にスマートフォンの業務利用が進む現代では、端末がセキュリティホールになるリスクが高まっています。
はじめに挙げられるのは情報漏えいリスクです。万が一、社員が誤って機密情報を外部に送信したり、悪意ある第三者が不正アクセスしたりした場合、企業に大きな損害を与えかねません。
総務省が公表している「情報通信白書」でも、モバイル端末の不正利用や紛失に伴う情報流出は中小企業にとって特に深刻な課題であると指摘されています。
次に業務効率の低下です。社用携帯が私的利用に偏れば、勤務時間中の生産性が低下し、勤務実態の把握も難しくなります。さらに、私的アプリの利用によるマルウェア感染など、セキュリティインシデントに発展するケースもあります。
また、法令遵守(コンプライアンス)の観点も欠かせません。金融業や医療業など個人情報を扱う業種では、社員の端末利用状況を適切に管理・記録することが求められています。監査対応や事故発生時の原因追跡のためにも、社用携帯の利用履歴を一定期間保存しておくことが望まれます。
要するに、社用携帯の監視は「社員を縛るもの」ではなく、企業と従業員を守るためのセーフティネットです。監視を適切に設計することで、安心して業務に集中できる環境を整えられます。
社用携帯の監視対象
社用携帯の監視といっても、その範囲には「できること」と「難しいこと」があります。監視可能な範囲を正しく理解し、過剰な監視や逆に不十分な管理を避けることが重要です。
このように、監視可能な範囲は「業務利用の健全性」や「セキュリティ維持」に直結する領域に限定されるのが一般的です。一方で、個人のプライバシーに踏み込みすぎる監視は法的リスクを伴うため、運用ルールの策定時に線引きを明確にする必要があります。
バックオフィスや情報システム部門が意識したいのは、「監視できること」と「監視すべきこと」を切り分けることです。必要最小限の範囲に絞ることで、従業員の安心感とセキュリティを両立できます。
社用携帯の監視方法
社用携帯を監視する方法にはいくつかのアプローチがあり、それぞれに特性と注意点があります。ここでは、代表的な3つの手法を解説します。
①MDM(モバイルデバイス管理)
最も一般的で実効性が高いのが、MDM(Mobile Device Management)の導入です。MDMを活用することで、企業は社用携帯を一元管理し、以下のような監視や制御が可能になります。
- アプリケーションのインストール制御
- OSやセキュリティパッチの更新状況確認
- 紛失・盗難時のリモートロックやデータ削除
- 利用状況やログの収集
MDMは「監視」と「管理」を両立させる仕組みであり、企業のセキュリティガバナンスを大きく強化します。特に従業員がリモートワークを行う場合、どの環境から業務データにアクセスしているかを把握できるのは大きなメリットです。
ただし、MDMの導入にはコストがかかるため、会社規模や利用台数に応じて適切な製品を選定することが求められます。
②位置情報の取得
社用携帯にはGPS機能が搭載されており、MDMやキャリアが提供する管理サービスを通じて位置情報を取得できます。これにより、以下の用途に役立ちます。
- 紛失・盗難時の端末追跡
- 勤務状況の確認(外出先業務や直行直帰の管理)
- 緊急時の従業員安否確認
位置情報の取得は企業にとって大きなメリットがありますが、同時にプライバシーに配慮する必要があります。例えば「業務時間内のみ位置情報を取得する」といったルールを設けることで、従業員の安心感を確保できます。
③通話履歴や検索履歴の取得
通話履歴については、発着信の記録を取得することが可能です。特に営業活動の状況や業務利用状況の把握に有効です。一方で、通話内容の録音を行う場合には、労働契約や法令上の制約に注意が必要です。
検索履歴の取得については、ブラウザや端末設定に依存するため、完全な把握は困難です。さらに、私的利用の範囲に深く踏み込む恐れがあるため、運用にあたっては「監視対象としない」方針を選ぶ企業も少なくありません。
総じて、通話・検索履歴の取得は「必要な範囲に限定すること」がポイントです。社員との信頼関係を損なわないよう、事前説明を徹底したうえで導入することが望ましいです。
社用携帯を監視する際の注意点
監視方法を導入する際には、単に「技術的にできるから行う」という姿勢ではなく、法令遵守や従業員の理解を前提に進めることが重要です。ここでは、監視運用における代表的な注意点を整理します。
運用ルールの策定
監視を始める前に必須となるのが、以下のようなルールを明文化することです。
- 監視の目的(セキュリティ強化・業務効率改善など)
- 監視対象範囲(位置情報・アプリ利用履歴など)
- データ保存期間と利用目的
これらを明確に文書化し、全従業員に周知することがコンプライアンス面でも求められます。
従業員への事前説明
監視対象やログ取得の有無を従業員に事前に説明し、理解を得ることが大切です。
「何を、どの範囲で、どのように取得するのか」を透明化することで、社員の不安を軽減できます。特に、私的利用に関するルールや監視の限界を明確に伝えることが、トラブル防止につながります。
運用のしやすさの確保
監視体制を継続的に運用するためには、効率的な仕組みづくりが欠かせません。新しいアプリのインストールやアップデート、ポリシー変更などを1台ずつ手作業で行うのは難しいため、MDM(モバイルデバイス管理)の導入を初期段階で検討します。MDMを活用すれば、端末設定の一括管理や自動更新、遠隔ロックなどが可能となり、担当者の負担軽減とセキュリティの維持を両立できます。
▼MDMの機能
- 端末設定の一括管理
- 自動更新
- 遠隔ロック
- アプリの管理 など
社内教育の実施
ルール策定や説明に加えて、以下の内容について定期的な教育が必要です。
- 私的利用によるリスク(情報漏えい、セキュリティ事故)
- 業務専用端末としての責任
- 安全なアプリ利用の方法
これらを周知することで、従業員が主体的に安全な利用を意識するようになります。監視は「管理側の強制」ではなく「従業員の意識改革」と組み合わせることで効果を発揮します。
セキュリティ対策
最後に重要なのが、監視と並行して以下のようなセキュリティ対策を進めることです。
- 端末の暗号化
- OS・アプリの自動更新設定
- 強固な認証(パスワード・生体認証・MFA)
監視が形骸化しないよう、技術的なセキュリティ対策と一体で進めることが、リスク低減につながります。
まとめ
この記事では、社用携帯について以下の内容を解説しました。
- 社用携帯の監視が必要な理由
- 社用携帯の監視対象
- 社用携帯の監視方法
- 社用携帯を監視する際の注意点
社用携帯の監視は、情報漏えい防止・業務効率向上・法令遵守といった観点から欠かせない取り組みです。しかし、監視の範囲や方法を誤ると、従業員からの反発やセキュリティリスクの逆流を招く可能性もあります。
成功のカギは、
- MDMによる効率的な一元管理
- 位置情報や通話履歴の適切な活用
- 明確な運用ルールと従業員への説明
- 教育とセキュリティ対策の両立
を実行に移すことです。
これらを自社だけで完璧に整えるのは難しいため、専門家や外部サービスの活用が有効です。バックオフィス担当者の方は、自社の状況に合わせた最適な社用携帯管理体制を構築してください。
『FGLテクノソリューションズ』の社内システム運用管理サービスでは、IT資産の管理やITインフラの構築・運用などをサポートしています。情シス部門・管理部門の負担軽減と安定したシステムの運用を実現します。