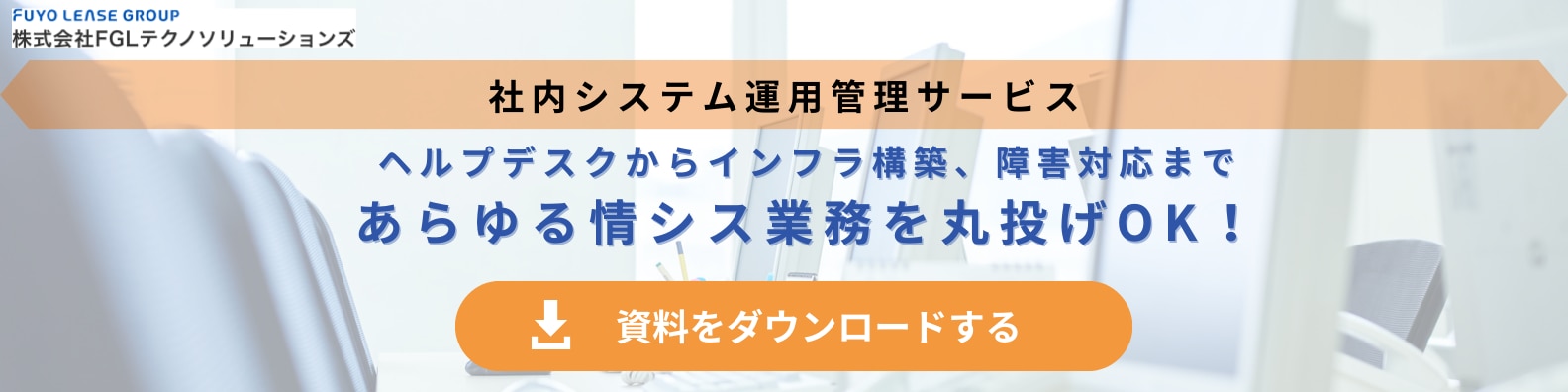ソフトウェア導入のよくある失敗と成功ポイント|ひとり情シスでも安心して進行する方法
業務効率化やDX推進の一環として、ソフトウェアの導入を検討する企業は増えています。しかし、導入プロジェクトが現場に使われない、定着しない、コストばかりかかるといった問題に直面するケースも少なくありません。特にひとり情シスの体制では、要件定義からベンダー対応、運用定着までを一人で担うことになり、負担が増えます。
この記事では、ひとり情シスでも安心して進められるソフトウェア導入の進行方法をテーマに、導入の流れ、失敗の原因、そして成功のポイントを具体的に解説します。
\調達・構築・管理などをワンストップで導入した事例はこちら/
\情シス向け!社内システムの運用管理業務のサポートはこちら/
目次[非表示]
- 1.ソフトウェア導入の流れ
- 1.1.要件定義とベンダー選定
- 1.2.PoCから本格導入まで
- 2.導入の失敗パターンと原因
- 2.1.現場ニーズとの不一致
- 2.2.運用ルール不足
- 3.ソフトウェアの導入する際のポイント
- 3.1.定着支援と運用改善
- 3.2.クラウドサービス活用
- 4.まとめ
ソフトウェア導入の流れ
ソフトウェアは導入して終わりではなく、計画・検証・定着までを含む長期的なプロセスです。
ただし、中小企業ではリソースや時間に限りがあり、「まずは少しでも業務を改善したい」「PoCなどに多くの工数を割けない」という現場も少なくありません。
そのため、完璧を目指すよりも、優先順位をつけて現実的に回せる導入を目指すことが重要です。
まず、導入する目的を明確にします。業務のボトルネックや手作業の多い部分、属人化している業務など、特に負担の大きい部分を洗い出します。
2.要件定義とベンダー選定
機能要件・セキュリティ要件・費用対効果などを整理し、複数のベンダーを比較検討します。「自社で扱えるレベルか」「初期設定やサポート体制が整っているか」なども重視しましょう。
3.PoC(実証実験)と導入検証
本格導入の前に小規模な環境で検証を行い、実運用に耐えうるかを確認します。ただし、本格的なPoCを行う余裕がない場合は、一部の部署や少人数で短期間の試行導入を行うだけでも十分です。ここで課題を早期に洗い出すことで、導入後のトラブルを防げます。
4.本番導入と教育
環境構築後は教育やマニュアル整備を行い、従業員が自走できる仕組みを整えることが大切です。導入初期はベンダーや担当者がこまめにフォローし、定着をサポートしましょう。
これらの流れを明確にしておくことで、ひとり情シスでも無理なくプロジェクトを進行でき、失敗のリスクを最小化できます。
要件定義とベンダー選定
要件定義は、ソフトウェア導入の成否を左右する重要な工程です。現場の課題をどう解決したいのか、どのような成果を目指すのかを明文化します。単に便利そうだから導入するのではなく、目的と期待効果を定量化することがポイントです。
また、ベンダー選定では価格だけでなく、サポート体制・導入実績・セキュリティ基準を確認します。特にクラウドサービスを導入する場合は、総務省が公開している『クラウドサービス利用のための安全対策ガイドライン』を参考に、データ保護や運用責任の範囲を明確にしておくことが重要です。
複数社から提案を受ける際には、比較表を作成し、客観的な基準で判断することも有効です。ひとり情シスでも、外部のITコンサルやベンダー担当者を巻き込み、共同で検討することでリスクを分散できます。
出典:総務省『クラウドサービス利用のための安全対策ガイドライン』
PoCから本格導入まで
PoCは、導入前にシステムの有効性を検証する段階です。このフェーズでは、現場業務に合うか、想定どおりの効果が出るかを確認します。PoCを省略すると、あとで思っていたのと違うというトラブルが発生しやすくなります。
もっとも、PoCは有効な検証手段である一方で、過剰な実証を繰り返すことでPoC疲れに陥るリスクもあります。目的や検証範囲を明確にしないまま複数ツールを試し続けると、導入判断が遅れ、現場のモチベーション低下を招く可能性があります。
そのため、PoCは導入可否を見極めるための最小限の検証にとどめ、一定の基準に達した段階で早期に意思決定へ移ることが重要です。検証項目としては、以下のような内容が挙げられます。
▼検証項目の例
業務フローとの適合性
操作性・UI(ユーザーインターフェース)の分かりやすさ
他システムとの連携
処理速度や安定性
セキュリティポリシーとの整合性
また、導入決定後は段階的に本番環境へ移行することが推奨されます。特にひとり情シスの場合、すべてを一度に切り替えるとトラブル対応に追われるリスクがあるため、部署単位・機能単位でのスモールスタートが現実的です。導入後は、利用者からのフィードバックを集め、改善を繰り返すことで運用を安定化させましょう。
\調達・構築・管理などをワンストップで導入した事例はこちら/
\情シス向け!社内システムの運用管理業務のサポートはこちら/
導入の失敗パターンと原因
ソフトウェア導入の失敗は、技術的な問題よりもコミュニケーションや運用の問題に起因することが多いです。
経済産業省の『DXレポート』でも、ITシステム導入が定着しない要因として、現場との乖離と運用体制の欠如が挙げられています。
出典:経済産業省:『DXレポート~IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な展開~』
現場ニーズとの不一致
多くの失敗要因は、“現場ニーズとシステムの不一致”にあります。情シスや経営層の判断で導入したものの、実際に使う現場の社員が求めている機能とズレているケースは少なくありません。例えば、入力項目が多すぎて運用負担が増えたり、既存の業務フローと合わなかったりします。
この問題を防ぐには、要件定義の段階で現場の声を拾うことが大切です。ヒアリングシートやアンケートを活用し、課題や希望を具体的に可視化します。また、PoC段階で現場代表者を参加させることで、実際の使い勝手を早期に確認できます。
ただし、現場の声をすべて採用してしまうと、システムが複雑化したり、導入スケジュールが長期化したりする恐れもあります。全てを一度に解決しようとせず、段階的に改善していくアプローチも効果的です。
さらに、導入後も利用データを分析し、定量的に効果を測定する仕組みを整えることが重要です。利用率やエラー発生率を指標にすれば、現場とのギャップを早期に発見できます。
運用ルール不足
もう一つの典型的な失敗パターンが“運用ルール不足”です。ツールを導入しても、使い方・権限・更新ルールが定まっていなければ、情報が混在し、システムが形骸化します。特にひとり情シス環境では、ルールを決める時間がない、現場任せにしてしまうといった状況が起こりがちです。
総務省が公表する『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』でも、システム運用における責任分担・権限管理・更新プロセスの明確化を求めています。
導入後は、誰がデータを登録し、誰が承認し、いつ見直すのかという運用フローを定めましょう。
出典:総務省『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』
ソフトウェアの導入する際のポイント
ソフトウェア導入を成功に導くカギは、定着支援と継続的な運用改善です。導入しただけで終わらせず、ユーザー教育と改善サイクルを組み合わせることで、全社的なDX推進につながります。
定着支援と運用改善
導入直後の定着支援が不十分だと、現場が使いこなせずにシステムが放置される危険があります。そのため、教育・サポート・改善の三段階で運用を支援する仕組みを作ることが重要です。
▼定着支援の3つのポイント
教育:操作マニュアルや動画チュートリアルを整備し、社員が学べる環境を整える。
サポート:ヘルプデスク体制を設け、質問やトラブルを早期解決できるようにする。
改善:利用ログやアンケートを分析し、課題を抽出して継続的な機能改善につなげる。
また、ユーザー代表を巻き込み改善会を定期開催することで、利用率向上にもつながります。このように、導入後の育てる運用を意識することで、情シス1人でもシステムを長期的に活用できます。
クラウドサービス活用
クラウドサービスを活用することで、ひとり情シスでも効率的にシステムを運用できます。SaaS(クラウド型ソフトウェア)は、導入スピードが速く、メンテナンスやセキュリティ更新をベンダー側で行ってくれるため、運用負担を軽減できます。特に、バックアップ・アクセス権限管理・監査ログといった運用面の機能が標準搭載されている点も強みです。
また、業務フローをシステムに合わせて見直すといった柔軟な対応も、SaaSであれば比較的実行しやすいのが特徴です。万が一、自社業務と合わなかった場合でも、サブスクであれば大きな初期投資を伴わずに解約・切り替えが可能です。そのため、中小企業でもリスクを抑えながら段階的に導入できます。
なお、導入前には、データ保護やサービス停止リスクへの対応方針を明確にすることが大切です。
まとめ
この記事では、企業におけるソフトウェアの導入について以下の内容を解説しました。
ソフトウェア導入の流れ
ソフトウェア導入の失敗パターンと原因
ソフトウェア導入の成功のポイント
ソフトウェア導入を成功させるには、目的の明確化、現場との連携、継続的な改善が欠かせません。ひとり情シスでも、段階的な導入とクラウド活用を組み合わせれば、無理なくプロジェクトを進められます。
導入失敗の多くは準備不足と運用軽視に起因します。要件定義からPoC、定着支援までを一貫して設計することで、導入効果を最大限に引き出せます。
システムは導入して終わりではなく、使われ続ける仕組みこそが成功の指標です。 ひとり情シスでも、確実な進行と継続改善で、社内DXを推進しましょう。
『FGLテクノソリューションズ』では、情シスの業務代行からIT利活用まで幅広い対応領域でITをフルサポートしております。システム導入等を検討している企業様はぜひご相談ください。
\調達・構築・管理などをワンストップで導入した事例はこちら/
\情シス向け!社内システムの運用管理業務のサポートはこちら/