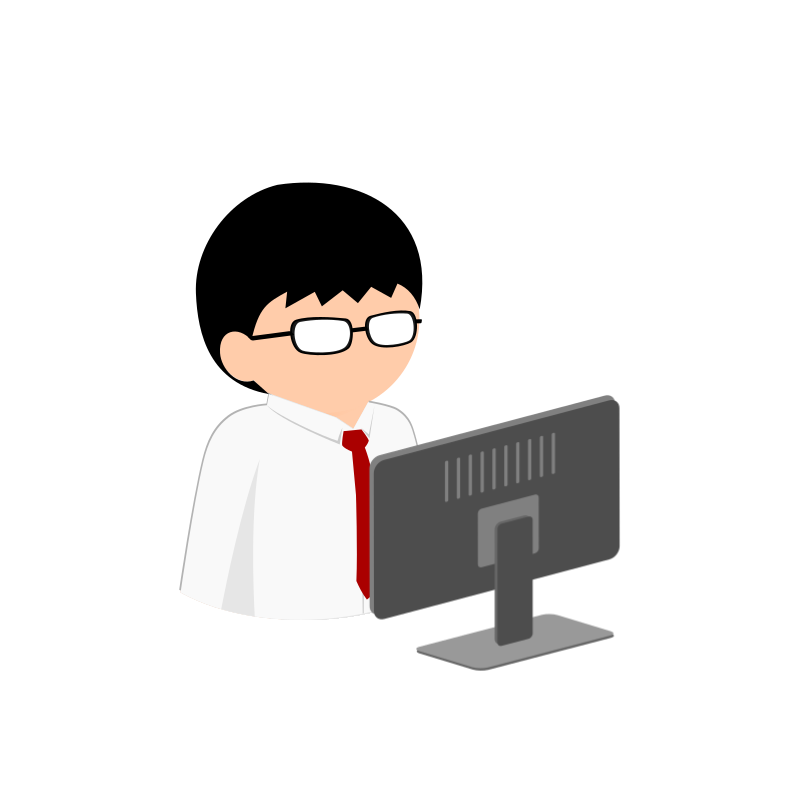情報システム(情シス)部門と社内SEの違いとは? 業務上の課題と円滑な運用に向けたポイント
情報システム部門(以下、情シス)では、業務を安全かつ円滑に行うために社内のサーバやシステムなどのIT基盤を運用・管理する役割を担っています。同じくITに関する業務を行う職種の一つに“社内SE(システムエンジニア)”があります。
どちらもITに関する業務であることや、人や会社によって情シス部門と社内SEの定義が異なる場合があることから、2つの違いについて混乱を招くことがあります。
企業のIT関連業務に携わる管理者のなかには「情シス部門と社内SEはどのような違いがあるのか」「円滑な運用を行うための対策はあるか」などと気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、一般的な定義としての情シス部門と社内SEの違いや業務上の課題、円滑な運用を行うためのポイントについて解説します。
目次[非表示]
情シス部門と社内SEの定義
情シス部門と社内SEの区分に明確な定義はありませんが、一般的には以下のように認識されています。
▼情シス部門と社内SEの定義
情シス部門 | 社内SE |
組織内でITインフラやシステムを運用・管理する部門 | システムの設計や開発を行う技術者 |
情シス部門は、企業のIT関連業務に対応する部門の一つに当たります。担当する業務の内容や範囲、運用体制などは企業によって異なります。
一方の社内SEは、従業員個人の職務や肩書きを指します。企業に属して社内システムの設計や開発などの専門的かつ技術的な業務を担当することが特徴です。
>>社内システム運用管理業務トータルサポートサービスに関する資料ダウンロードはこちら
情シス部門と社内SEの違い
情シス部門と社内SEは、対応する業務の領域に違いがあります。どちらもITに関連する業務に対応しますが、情シス部門のほうがより広域となっています。
▼情シス部門と社内SEの違い
業務内容 | 具体例 | |
情シス部門 | 社内システムの運用管理や社内へのIT技術の浸透 |
|
社内SE | 社内システムの開発・保守 |
|
情シス部門は、社内システムを安定稼働させるための運用管理を行うだけでなく、ITの利活用によって業務課題の解決や経営目標を達成するサポートを行います。一方の社内SEは、社内システムの開発や保守対応が中心となります。
全社的なITインフラの運用管理を担う情シス部門とは異なり、社内SEは対象が社内システムのみに区別されることが一般的です。ただし、企業によっては情シス部門の一部に社内SEが含まれる場合もあります。
なお、情シス部門の役割についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
情シス部門と社内SEにおける業務上の課題
社内システムの開発や保守を担う社内SEがひとりしかいない職場では、情シス部門と兼任して単独で業務を行っているケースがあります。
しかし、情シス部門の業務と社内SEの業務の両方に対応する必要があり、さまざまな課題を招きやすくなります。
▼情シス部門と社内SEの業務を単独で行う場合の課題
- ヘルプデスクやトラブル対応など日々の業務に追われ、IT戦略の立案まで手が回らない
- 日々の業務量が過多になり、担当者の労働環境が悪化する
- 社内SEに必要な知識・技術をアップデートする時間を確保できず、スキルアップ・キャリアアップが難しい
- 対応が属人化して担当者が不在のときや退職時に業務を引き継げなくなる
- 対応する業務量や範囲が広く、急なトラブルへの対応が遅れる など
なお、IT人材不足への対策についてはこちらの記事をご覧ください。
情シス部門と社内SEの業務を円滑に運用するポイント
情シス部門と社内SEの兼任による課題を解決するには、IT関連業務を分担・分離してリソースの配分を最適化したり、複数の担当者でフォローし合える体制を整備したりする必要があります。
①コア業務とノンコア業務を切り分ける
情シス部門の業務による担当者への負担を軽減するために、コア業務とノンコア業務を切り分けて対応する方法があります。
ITに関する専門的な知識・技術・ノウハウが求められる業務についてのみ、情シス部門の担当者が対応できる運用体制を構築することがポイントです。
▼コア業務とノンコア業務の例
コア業務 | ノンコア業務 |
|
|
現場のサポートや事務作業などを中心としたノンコア業務をほかの従業員と分担して対応することで、情シス部門の担当者がコア業務に注力できる環境となります。
②マニュアル・社内FAQを作成する
社内ヘルプデスクに持ち込まれる相談の数を減らすために、マニュアルや社内FAQを作成することも有効です。
業務部門の従業員が疑問点やトラブルを自己解決できる環境を整えることで、社内ヘルプデスクの対応を減らせます。
▼マニュアルや社内FAQに記載しておく情報
- 社内システムやIT機器の操作方法
- よくあるトラブル・エラーの対処方法
- IT機器の仕様書や管理方法 など
また、情シス部門が対応する業務のナレッジ・ノウハウを蓄積できるツールを導入することで、担当者が不在のときのフォローや引き継ぎを行いやすくなります。
③ITアウトソーシング(業務代行)を活用する
情シス部門が担当しているノンコア業務について、ITアウトソーシング(業務代行)を活用することも一つの方法です。
ITアウトソーシングを活用すると情シス部門で対応する業務量が削減されて、システムの企画・開発やIT戦略の立案などのコア業務に専念できるようになります。
また、情シス部門の業務に対応するリソースを増やすことで、トラブル対応の迅速化や運用管理品質の向上も期待できます。社内SEが情シス部門を兼任する必要がなくなれば、スキルアップ・キャリアップのための時間を確保しやすくなり、IT人材育成の促進にもつながります。
なお、ITアウトソーシングの方法についてはこちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
まとめ
この記事では、情シス部門と社内SEについて以下の内容を解説しました。
- 情シス部門と社内SEの一般的な定義
- 情シス部門と社内SEの違い
- 情シス部門と社内SEにおける業務上の課題
- 情シス部門と社内SEの業務を円滑に運用するポイント
情シス部門と社内SEは、一般的な定義が異なるほか、対応する業務の領域に違いがあります。情シス部門は社内のIT関連業務を広域的に行うのに対して、社内SEは主にシステムの開発・保守といった技術的な業務のみに対応します。
それぞれの業務を兼任して単独で業務を行っている場合には、業務負担の増加や属人化、トラブル対応の遅れなどのさまざまな問題を招くおそれがあります。
円滑に運用するには、コア業務とノンコア業務を切り分けてリソースを配分するとともに、マニュアル・社内FAQを作成して社内ヘルプデスクの対応を減らしたり、ITアウトソーシングを活用したりすることがポイントです。
『FGLテクノソリューションズ』の社内システム運用管理サービスでは、ITインフラの運用管理やシステム開発など、情シス部門におけるあらゆる業務の代行を行っています。約30年にわたって蓄積した経験とノウハウを基に、専門的かつ幅広いIT業務をサポートいたします。
サービスの詳細については、こちらの資料をご確認ください。