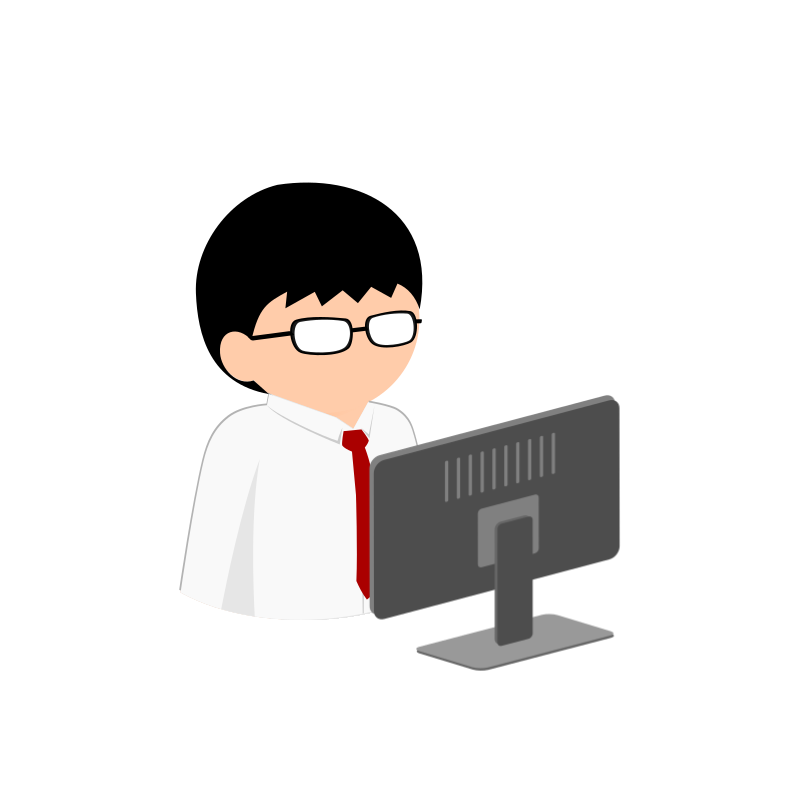クラウドサービスによる業務の運用を安全かつ効率的に行う方法
クラウドサービスは、いまや社会経済活動に欠かせないICT基盤となっており、主要な業務システムをオンプレミス環境からクラウド環境へ移行している企業も多く見られています。
業務の効率化や多様な働き方の実現を後押しするクラウドサービスですが、運用にあたってはいくつか懸念点もあります。
企業の業務システムにクラウドサービスを利用する際は、懸念点を踏まえて安全かつ効率的に運用できる体制を整えておくことが重要です。
この記事では、情報システム部門・管理部門の担当者に向けて、業務にクラウドサービスを利用することによる効果や懸念点、安全かつ効率的に運用する方法について解説します。
目次[非表示]
業務にクラウドサービスを利用することによる効果
クラウドサービスは、社内に物理的なサーバを設置することなく、スマートフォンのアプリケーションやWebブラウザ上で利用するサービスです。
オンプレミスで運用していた業務システムをクラウドサービスに移行することにより、以下の効果が期待できます。
▼クラウドサービスによって期待できる効果
- 場所を選ばずに業務を行える
- 設備調達や保守運用のコストを抑えられる
- 拡張性を確保できる など
主要な業務システムをクラウドサービスに移行すると、インターネット環境があれば場所・端末を問わずにアクセスすることが可能です。自宅や外出先でも業務を継続できるため、効率的かつ柔軟な働き方の実現につながります。
また、サーバ・ハードウェア・ソフトウェア・データなどを自社で保有・管理する必要がなくなるため、設備調達や保守運用にかかる労力とコストの削減を図れます。さらに、ユーザー数の増減やオプション機能の追加などを迅速に行えることから、事業の拡大に伴う利用規模の変化にも柔軟に対応しやすくなります。
>>社内システム運用管理業務トータルサポートサービスに関する資料ダウンロードはこちら
クラウドサービスを利用する際の懸念点
クラウドサービスでは、クラウド事業者と利用者に責任管理範囲がある“責任共有モデル”が採用されています。提供形態によって責任範囲が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
▼クラウドサービスを活用する際の懸念点
- セキュリティ上のリスクがある
- 障害によってデータが消失するリスクがある
- カスタマイズの内容・範囲に制約がある
- 利用量の増加によって使用料が高くなる可能性がある など
従業員によるパスワード管理やアクセス制限などに問題があると、第三者による不正アクセスが行われて情報漏えいにつながるリスクがあります。
また、クラウドサービスの保守管理はクラウド事業者が対応しますが、事業者側の設定不備によって機密情報が流出した事案も増加しています。障害が発生した場合には保存されたデータが消失してしまい、業務の継続に支障が出る可能性があることもリスクの一つです。
さらに、カスタマイズを行える内容・範囲は各サービスで定められているため、自社の業務に必要な機能を確保できない可能性があります。従業課金制の場合には、容量やユーザー数が増加すると使用料が高くなるため、オンプレミスでの運用と比べてコストが負担となる可能性も考えられます。
なお、クラウドサービスのセキュリティ対策を強化する方法や各形態の責任範囲についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
クラウドサービスで安全かつ効率的に業務を運用する方法
クラウドサービスを利用する際には、自社の業務内容やクラウド事業者の管理体制などを踏まえて、安全かつ効率的に業務を遂行できる対策を講じることがポイントです。
➀アカウントのセキュリティ管理を行う
クラウドサービスへの不正アクセスを防ぐには、アカウントのセキュリティ管理を行うことが重要です。
従業員の管理不備によるパスワードの流出を防ぐとともに、権限のないユーザーからのアクセスを制限することにより、セキュリティを向上できます。
▼アカウントに対するセキュリティ管理の具体例
- パスワード管理のルールを示したマニュアルを作成して共有する
- 従業員の業務内容や役職に応じてアクセス権限を設定する
- 複数の要素を組み合わせた認証方式を設定する など
アカウントのセキュリティ管理を行う際は、クラウドサービスのIDを一元管理して、ユーザーの情報やアカウントの使用状況、権限の設定状況などを把握できる仕組みが必要です。また、オンプレミス環境と異なり、インターネット接続で直接的に不正アクセスされやすいため、特権IDの厳重な管理も重要です。
なお、ID管理を効率化する方法についてはこちらの記事で解説しています。
②定期的にバックアップを実施する
クラウドサービスに保存したデータについては、定期的に社内のサーバや物理的な記録媒体などに複製してバックアップをとっておく必要があります。
クラウドサービスには、自動でデータのバックアップを行う機能が備わっていることが一般的です。しかし、障害によって一時的に停止したり、サービスの提供が終了したりすると、業務に必要なデータを使用できなくなる可能性があります。
定期的にバックアップを行うことで、万が一の際に重要なデータの消失を防げるほか、業務の一部を継続できるようになり損害を最小限に抑えられます。
▼バックアップをとる方法
- クラウドバックアップサービスを利用する
- 社内にバックアップサーバを設置してデータを保管する
- 社内PCに内蔵・外付けされたハードディスクやUSBメモリに保存する など
また、永続的または長期的に保管が必要なデータや、情報資産をスムーズに参照して業務に活用したい場合などは、検索性を確保したアーカイブを作成することも有効です。
バックアップについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
③プライベートクラウドを活用する
自社の業務に合わせてクラウドサービスをカスタマイズしたい、セキュリティを高めたい場合には、プライベートクラウドを活用することも一つの方法です。
プライベートクラウドとは、利用者の要件に合わせてクラウドサービスを構築する利用形態です。クラウド事業者が提供するサービスの範囲内で利用する“パブリッククラウド”と比べてカスタマイズ性が高くなります。また、ほかのユーザーとリソースを共有しないため、セキュリティレベルが高い点も特長の一つです。
「パブリッククラウドのサービスだけでは必要な機能を確保できない」「既存の業務システムと同じ機能を備えたい」「もっとセキュリティを強化したい」といった場合に適しています。
▼プライベートクラウドの種類
種類 |
概要 |
オンプレミス型 |
社内にサーバや機器を設置してクラウド環境を構築・運用する方法 |
ホスティング型 |
サービス事業者と契約した範囲内で要件に合ったクラウド環境を構築・利用する方法 |
なお、注意点としてオンプレミス型のパッケージ製品をプライベートクラウドで利用する場合は、ライセンス契約の確認が必要です。ユーザー別でライセンスが必要になったり、追加で費用の支払いが必要になったりする場合があります。さらに、製品によってはクラウドサービスでの利用を禁止しています。
④運用コストを管理する
クラウドサービスを効率的に利用するには、運用コストの管理が欠かせません。導入時にかかる初期コストだけでなく、利用状況の変化を踏まえて予算の設定やリソースの調整などを行うことが重要です。
▼運用コストを管理する際のポイント
- クラウドサービスの予算と実際にかかった運用コストの差異を確認して予実管理を行う
- 利用規模の変化に応じてプランや課金設定を変更する
- クラウドサービスの利用料だけでなく間接費も予算に含める
- 海外のクラウドサービスは為替レートを考慮する など
なお、クラウドサービスのなかには運用コストを管理できる機能が備わったものもあります。
まとめ
この記事では、クラウドサービスについて以下の内容を解説しました。
- 業務にクラウドサービスを利用することによる効果
- クラウドサービスを利用する際の懸念点
- クラウドサービスで安全かつ効率的に業務を運用する方法
クラウドサービスを業務に利用すると、効率的かつ柔軟な働き方につながるほか、設備調達や保守運用の労力・コストを抑えられる、利用状況の変化にも対応できるといった利点があります。
自社の業務内容やクラウド事業者の管理体制などを踏まえて、安全かつ効率的にクラウドサービスを活用できる対策を講じることがポイントです。
また、クラウドサービスを運用するには、アカウントの管理やセキュリティ対策、自社の業務内容に応じたカスタマイズの検討などが必要になります。自社での対応が難しい場合には、ITアウトソーシング(業務代行)を活用することが有効です。
『FGLテクノソリューションズ』の社内システム運用管理サービスでは、クラウドサービスの選定やIT環境の構築、アカウントの管理などのさまざまな業務をサポートしています。オンプレミス環境からクラウド環境への移行もお任せください。
サービスの詳細については、こちらから資料をダウンロードしていただけます。